Ebina City Oya Junior High School
学校概要
学校教育目標
自立・夢を拓く人
(1)豊かな心 (2)深める学び (3)健やかな体 (4)社会とのふれあい
実践の指針
(1) 「豊かな心」
人間関係づくりを育む指導を土台とし、すべての生徒にとって安心感があり、自分のよさを認め、他者を思いやり、誰かのために自分にできることを実践す
る心を育む学校を目指す。自分の考えを持った上で、他者を尊重し、建設的な
人間関係づくりを目指す中で、協働し創造する意欲、失敗を恐れず困難に立ち
向かう意志、自らの判断や行動、その結果に責任をもつ自立した心を育てたい。
(2) 「深める学び」
基礎的な学力と課題解決型の学力は両輪である。課題解決とは自ら「問い」を立て仲間とともに考え、自分なりの答えを見出そうとする、学びの深まった
状態の一つと考えられる。
基礎学力の定着を図るため分かる授業の研究を進め、指導方法の工夫改善と
ともに、家庭学習を含めた学習の習慣化を目指す。また、基礎学力の一つとし
て、教育活動全般を通して文章を読む・書く機会を意図して設け、語彙を増や
し目的に合った文章を抵抗なく書く力を育てたい。
課題解決型の学力の育成には「対話」を重視する。対話する必然性のある学
習場面の設定に努め、自分の考えや問いを持ったうえで、他者の意見から新た
な「気づき」を得ようとする姿勢を育てる。また、教科等横断的な学びを意図
的に進め、つながりから学びが深まるよう意識する。
(3) 「健やかな体」
健康・体力の増進を図る。基本的生活習慣を整え、気力・体力の向上を図り、目標に向かって粘り強く
チャレンジする生徒を育てる学校を目指す。
学校で効果的に活動できる状態を常に保持できるよう、生活習慣の見直しと
改善を家庭と連携を図りながら進める。
(4) 「社会とのふれあい」
地域行事への単なる参加に留まらず、自らの学びを地域・社会で生かそうとする意欲を育て、主体的に関わる機会を工夫したい。
「社会に開かれた教育課程」の趣旨を踏まえ、「学びが世の中とつながって
いるか」という視点をもつ。学びが学校内で完結し受験に収斂されていく学び
に留まっていないか、将来どうなりたいかが学びの動機となっているか、とい
った課題意識をもって教育活動を点検し向上させる姿勢を大事にする。
今年度の重点目標
「語ろう思い 伝えよう願い」
令和6年度は、重点目標を「応援される学校」とし、本校の実践指針「社会と
のふれあい」に焦点を置き教育活動を推進してきた。教育課程を社会(地域)に
開くことで、地域・学校の協働及び地域への社会貢献に重点を置いた取組も進め
ることができた。
この取組は、学校が、地域のランドマークであることを前提とし、子どもたち
の学びや活動を地域とつなぎ、社会の一員としての自覚を高め、よりよく生きて
いく力を育むことを目的として進めてきたが、「応援される学校」として地域から
の参画が十分であったかという点については、今後の課題が残る。
令和7年度は、この取組を継承する中、「総合的な学習の時間」や「特別活動」
など、これまでの学習活動の過程やその在り方を見直し、子どもたちが、日常の
生活や各教科を通して学んだことをいかし、自らの目的(テーマ)をもち、社会
とのつながりの中で、探究的に学び、人とのつながりの中で、実生活に結びつく
「生きて働く力」に実感をもつことができるよう、その資質能力の育成を図りた
い。
このことを踏まえ、令和7年度の重点目標は、「語ろう思い・伝えよう願い」と
する。これは、子どもたちの自己実現に向けた、自己との対話や他者との協働的
な学びを支えるとともに、海老名市が推進する「フルインクルーシブ教育」を手
掛かりに、多様な他者とのかかわりの中で、「ことば」のもつ力の大切さを理解し、
自らの思いを語り合う子どもたちの育成を図りたい。
また、子どもたちが、体験的な活動を通して出会う、様々な人や事象とのかか
わりの中で、自らの生き方を見直し、他者(地域)貢献についての考えを深める
過程において、さらなる願いをもつことをめざし、1年間の教育活動の歩みを進
めたい。
教育課程
| 学年\教科 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 音楽 | 美術 | 保体 | 技家 | 総合 | 道徳 | 特活 |
| 1年 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2年 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3年 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
日課
※生徒登校は8:30、 日課表中の数字は授業数
| 時間 | 日課 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 8:40~8:45 | 朝読書・朝学習 | |||||
| 8:45~8:50 | 朝の会 | |||||
| 9:00~9:50 | 1校時 | 1 | 道徳 6 |
学活 12 |
18 | 24 |
| 10:00~10:50 | 2校時 | 2 | 7 | 13 | 19 | 25 |
| 11:00~11:50 | 3校時 | 3 | 8 | 14 | 20 | 26 |
| 12:00~12:50 | 4校時 | 4 | 9 | 15 | 21 | 27 |
| 12:50~13:25 | 昼食 | |||||
| 13:25~13:40 | 休憩 | |||||
| 13:45~14:35 | 5校時 | 総合 5 |
10 | 16 | 22 | 28 |
| 14:45~15:35 | 6校時 | 11 | 17 | 総合 23 |
29 | |
| 15:40~15:50 | 清掃 | |||||
| 15:55~16:05 | 帰りの会 | |||||
| 16:15(16:00) | 生徒下校 | |||||
最終下校時刻
※17日〜
| 時刻/月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 夏休み | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 17:00 | ○ | ※○ | ○ | ○ | |||||||||
| 17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
生徒数・職員数
生徒数(2025年4月30日 現在)
| 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援学級 (はるかぜ級) |
合計 | |
| 男 | 98 | 82 | 94 | 7 | 281 |
| 女 | 89 | 84 | 89 | 5 | 267 |
| 合計 | 187 | 166 | 183 | 12 | 548 |
| 学級数 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 |
| 教職員 | 校長 1名、教頭 1名、教諭 32名、栄養教諭1名、養護教諭 1名、事務職他 1名 |
校長・教頭
学校長 小林 丈記 教頭 大矢 貴史
このページの先頭へ
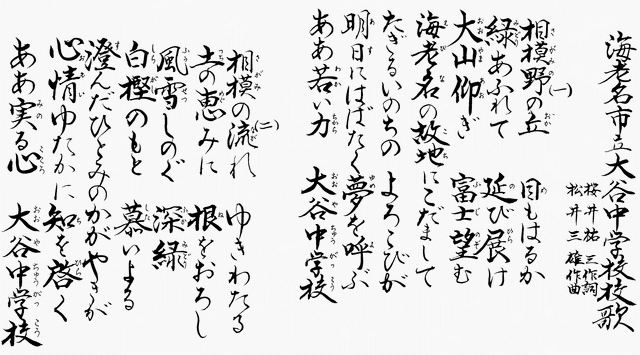
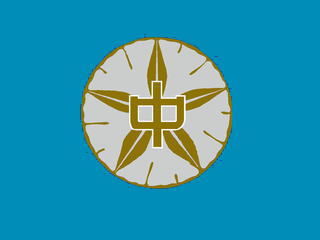
大谷中付近の極相林であるシラカシの葉と県の木イチョウの葉5枚を円の中に収め、
中央の「中」の字でまとめた。シラカシの5枚は、市内5番目に誕生したことを表す
とともに大谷中の「大」の文字を表し、周囲の人々の暖かい理解のもと、すくすく伸
びることを願った。また、「中」の字は中学校の中であると同時に中庸を意味し、円
満な人間性と限りない発展を願ったものである。校章をとりまくセルリアンブルーが
スクールカラーである。なお、セルリアンブルーは白樫の森を遠望したときに見える
色であると言われている。
校歌
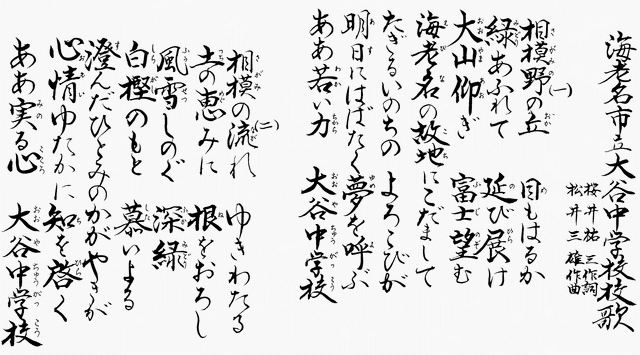
校章
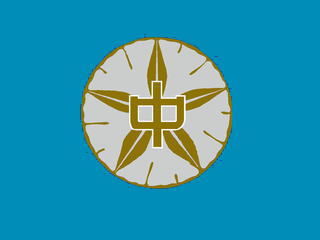
大谷中付近の極相林であるシラカシの葉と県の木イチョウの葉5枚を円の中に収め、
中央の「中」の字でまとめた。シラカシの5枚は、市内5番目に誕生したことを表す
とともに大谷中の「大」の文字を表し、周囲の人々の暖かい理解のもと、すくすく伸
びることを願った。また、「中」の字は中学校の中であると同時に中庸を意味し、円
満な人間性と限りない発展を願ったものである。校章をとりまくセルリアンブルーが
スクールカラーである。なお、セルリアンブルーは白樫の森を遠望したときに見える
色であると言われている。
海老名市立大谷中学校
〒243-0418
神奈川県海老名市大谷南2-10-1
TEL 046-233-3233